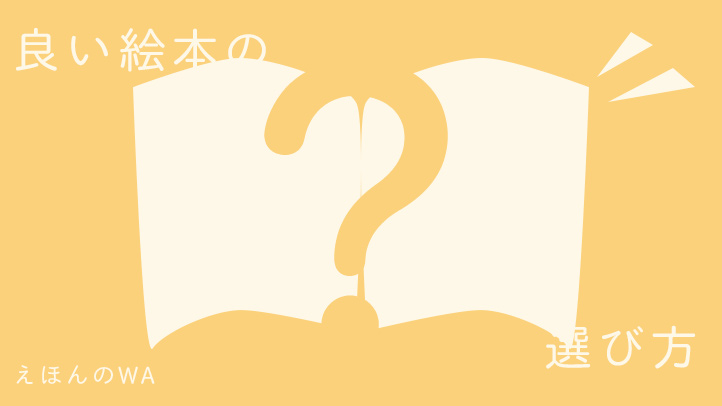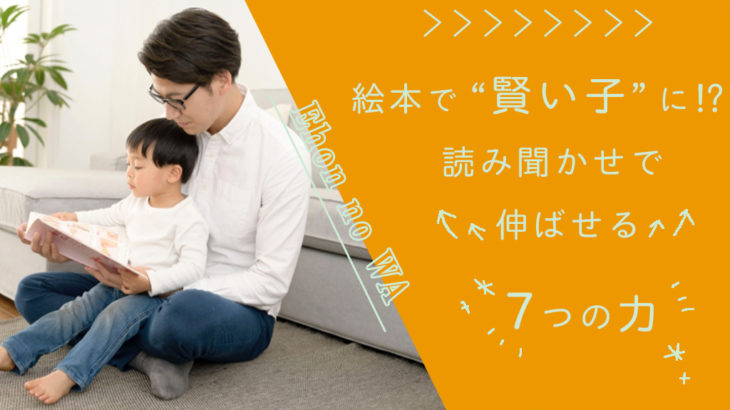ナンセンス絵本、というカテゴリーの絵本が存在するのをご存知だろうか。
“ナンセンス”の言葉の意味を辞書なんかで調べてみると、【意味をなさないこと。無意味であること。ばかげていること。また、そのさま。ノンセンス。】*などなどまあまあ酷い言われようなのだけど、じゃあナンセンス絵本がばかげて意味のない絵本なのかというと全くそんなことはない。
むしろ、意味、大有りな絵本である。
ナンセンス絵本が教育に良いワケ①優れた想像力
ナンセンス絵本、というのは先述の通り無意味な絵本でもなければ何も考えずに作られた絵本でもない。
構成なんかは一般的な絵本よりも遥かに考え抜かれ、練られた作品が圧倒的に多かったりする。
何といっても、面白い。とにかく面白い。
人間、面白いことを考えるときというのはめちゃくちゃ頭を使うのである。長年人気を集めているベテランお笑い芸人の方々がわかりやすい例であり、最強のユーモアセンスというのは優れた知性からしか生まれない。
そういえば、何かの番組で東大生の推し芸人No.1はミルクボーイだということを知った。テンプレ化と汎用性が神がかっている(ビジネス的視点で)からだそうだ。

ナンセンス絵本が教育に良いワケ②圧倒的独創性
絵本には、起承転結の型のようなものがある程度は存在する。その既存の概念をいとも簡単にぶち破ってしまうのがナンセンス絵本なのだ。
次にどうなりそう・・・という読者の予想を良い意味で裏切る。
そもそも次の展開が読めな過ぎる。
という未知の想像の世界に足を踏み入れられるのがナンセンス絵本の魅力だ。
これからの時代、常識を打ち破る圧倒的な独創力というのは未来を切り拓く重要なキーになるに違いない。
子どもの未来の可能性は無限大。ナンセンス絵本はその力を引き出してくれる。

ナンセンス絵本が教育に良いワケ②親も楽しい、教育の肝
月曜日は塾に行かせて火曜日はスイミング、水曜日は習字で木曜はピアノ・・・。
と息を切らしながら送り迎えを頑張っている親御さんもいるかもしれない。
はたまた、1日10冊、毎日読み聞かせするのが鉄則!とスピードラーニングかのごとく絵本のシャワーを浴びせているパパママもいるかもしれない。
とっても素晴らしいことだけど、結構疲れることは間違いない。
親が疲れてしまうような教育は、子も疲れる。
親が楽しく没頭できるような教育は、言われなくても子も自ら進んで実践するようになる。
楽しい!面白い!もっと知りたい!
これが教育、そして学びの肝である。
親子で楽しめるのが絵本の読み聞かせの最大の利点であり、ツールとしてのナンセンス絵本はその最たるものである。
もっと読み聞かせを楽しもう。
推しのナンセンス絵本①『キャベツくんのにちようび』
長 新太 文研出版
絵本好きで長新太氏を知らない者はいないはず。
彼は【ナンセンス絵本の神様】という神々しい異名を持つ。
著書である『ゴムあたまのポンたろう』という絵本を読んだとき、しかくい頭をまるくするって、こういうことか!と目から鱗が落ちたのは今でも忘れられない。
そんな長氏の傑作『キャベツくんのにちようび』に出会ったときもまた異常な衝撃を受けた。
また、ヤバい絵本が登場してしまった。
幼少期ながら頭に雷が落ちたような感覚で読んだのを覚えている。
親と子、涙を流すほど笑って楽しんで欲しい。
暗いニュースばかりが流れる今、気分がパッと明るくなる1冊だ。
Amazonアソシエイト
ちなみに『キャベツくんのにちようび』を楽しんだ極度の絵本マニアには下記もおすすめ。
『むしむしでんしゃ』
内田 麟太郎 (著), 西村 繁男 (イラスト) 童心社
Amazonアソシエイト
著者の内田氏は長新太氏に私淑。(言葉の魔術師ともいわれている。)
長氏へのリスペクトが詰まった作品で、仕掛けに気づいたファンは興奮するに違いない。
推しのナンセンス絵本②『だれのパンツ』
シゲリ カツヒコ (著) KADOKAWA
シゲリ氏の描く絵はとにかくインパクト大。誰しも一度見たら忘れないだろう。
人物やキャラクターの表情描写がともかく愉快で、そこを追っていくだけでも楽しい。
が、本作品で追うのは表情ではなく“パンツ”の持ち主である。
タイトルに“パンツ”の3文字が入っていて、面白くないわけがない。
腹を抱えて笑える作品なのは間違いないが、絵本としてだけでなくアートとしても堪能できるのがシゲリ氏作品の偉大なところである。
現代アート好きにはたまらない1冊だ。
Amazonアソシエイト
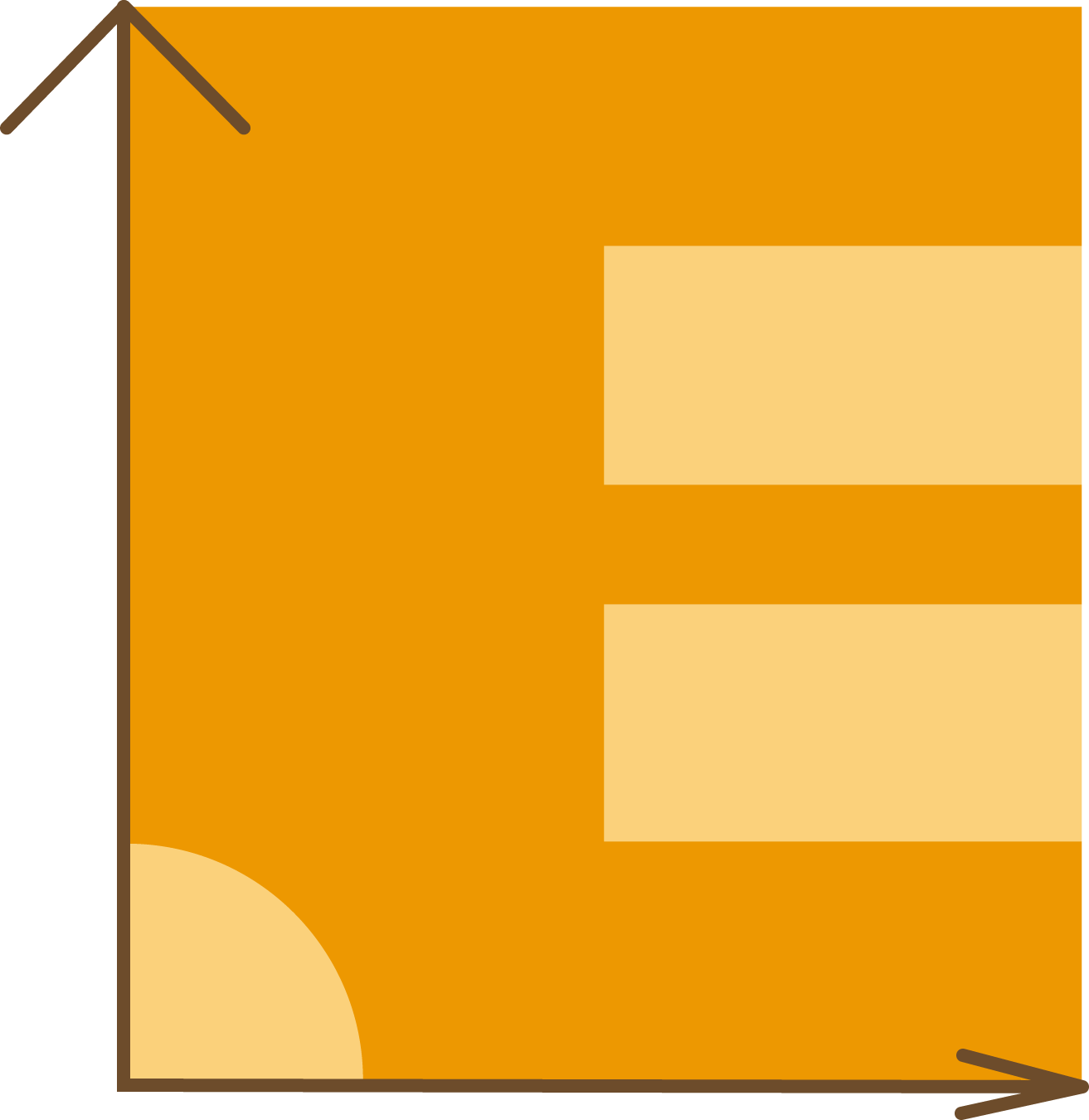

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a8b4bd.f1400b72.20a8b4be.0901995f/?me_id=1251035&item_id=11454152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2F2838000%2F2837658.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c388f08.5fc5e008.1c388f09.f3b430f7/?me_id=1213310&item_id=19643554&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6989%2F9784041076989.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)