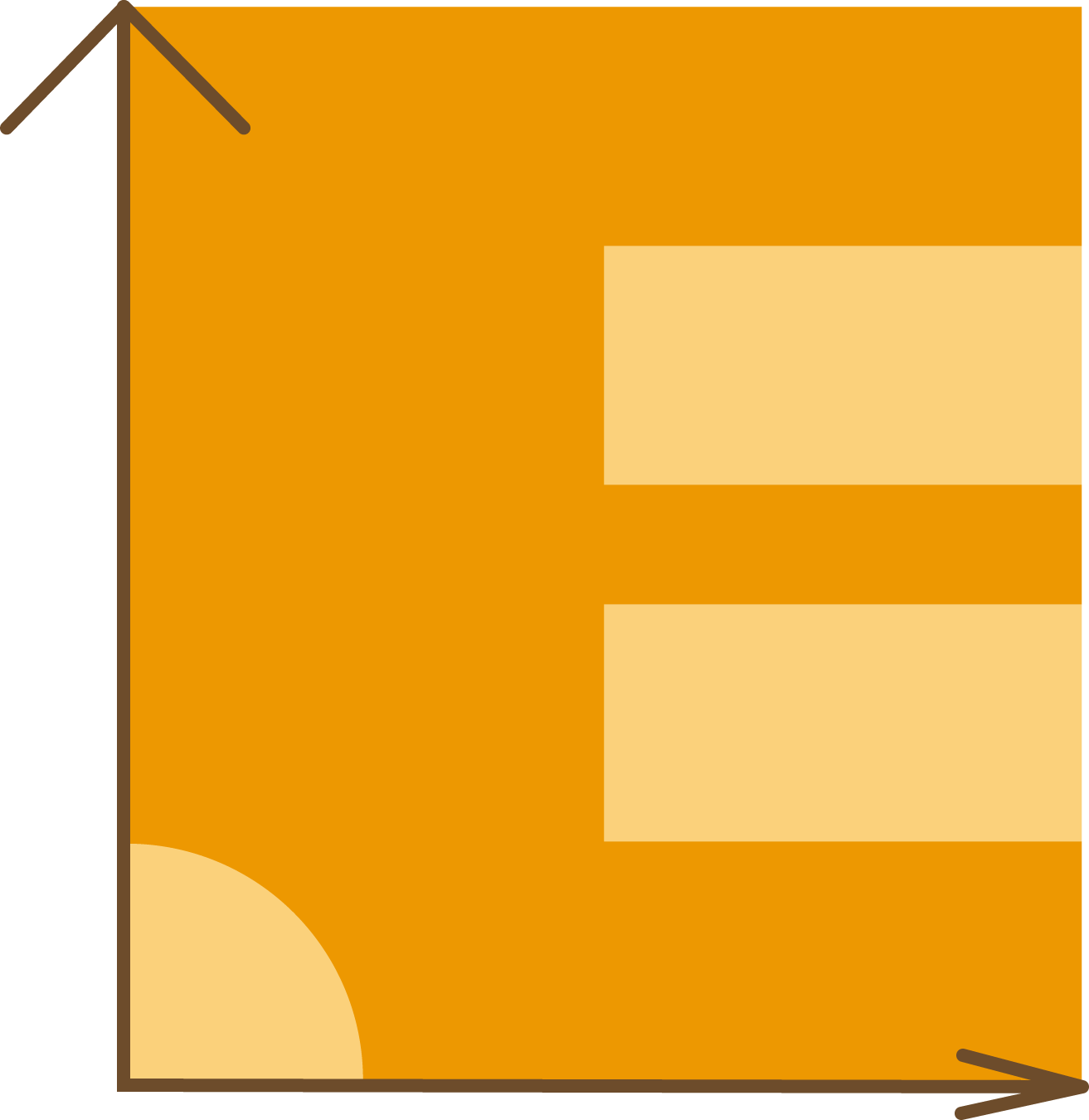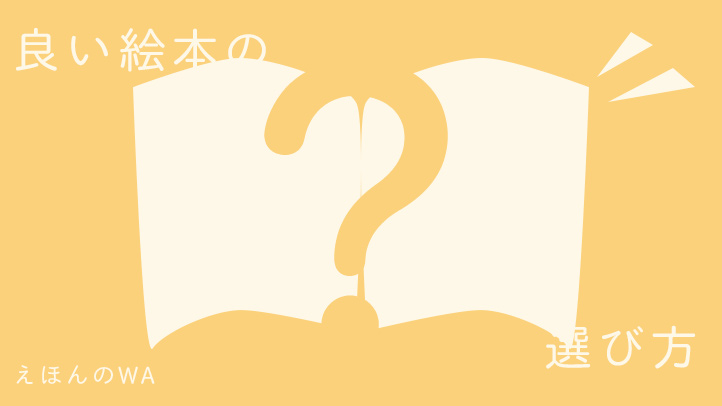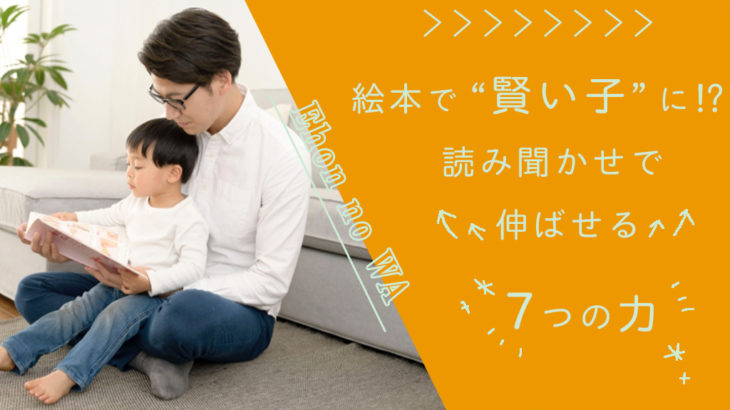「なんで最後まで聞いてくれないんだ・・・!?」
(せっかく買ったのに。結構この絵本高かったのに・・・!○○大学の教授絶賛とか書いてあったのに!!)
そう思ったことはないだろうか。
途中で読むのやめてどっか行っちゃうから、この子、この本に興味ないんだわ(泣!)と判断するのは実は早い。
数回だけ読んで(うちの子コレ、読まないわ!!)と諦めてしまう方はちょっと待って欲しい。
コツ①最後まで聞いてもらおうとか思わない
まず絵本云々というより、0~1歳くらいの子が決められた時間集中力を持ってじっとしている、というのは並大抵のことではない。
ちょっと話は逸れるけれど、大人でも慣れない運動とか、慣れない試験勉強とか、「毎日○○時間やるぞー!!」みたいな目標を立てても最初は難しい。
ましてや赤ちゃんや1歳の子に数分間じっとして話を聞いていろ、というのは非現実的で酷な話である。
かと言ってこの時期の子に絵本の読み聞かせは意味が無いのかというと、むしろ逆で、なんなら生まれた瞬間(もはや生まれる前)からどんどんやっていった方が良い。
最後まで聞いてくれなくとも、周りの大人が絵本を読み聞かせすることで五感から入ってくる情報の刺激たるや、脳みそが踊り狂うくらいの刺激と効果がある。
(個人差はあるけれど)
最初の3ページ聞いてくれるだけで、ひとまずは十分、万々歳!くらいの心持ちでいたい。

コツ②習慣化の爆発的効果
人間たる者、慣れないことを集中して実行するハードルが高い性分である、という話をした。
一方で、趣味の何か、ゲームでもアニメでも、ドはまりしていることというのは気が済むまでいくらでも集中していられる。やめろと言われてもやっていられる。
ドラマの続きが気になってイッキ見してみる、ゲームの続きが気になってつい課金してみる…
そんな感じで毎日やらないとソワソワすること、誰しも1つや2つあるのではないだろうか。
絵本の読み聞かせも、この習慣化が肝なのだ。
習慣化さえしていれば、「絵本を読む」という行動そのものに“慣れ”が出てくる。結果、3歳頃には比較的長文の絵本も最後まで楽しみながらじっと聞いていることができるようになる。
コツ③程よい習慣化がキモのキモ
習慣化するというと、時々「毎日読まなくちゃ!死ぬほど疲れているけど毎日読まなくちゃ」だとか「毎日10冊以上読む!鉄則!家訓!」みたいな超ストイックな方も意外と出てくる。
心意気は間違いなくとても素晴らしいのだけど、実はこれだと習慣化するのに逆効果な可能性が高い。
子どもは楽しいことだけやりたい生き物だ。
ストイック型の読み聞かせだと、義務感が発生する。義務感が出ると、子どもが楽しくなくなるのはもちろん、読んでいる大人もなんだか楽しくない感じになって負のループに陥ってしまう。
絵本の読み聞かせで一番大事なのは子も大人も楽しむこと
これに尽きる。
心に余裕のある日には存分に楽しんで、「今日は無理!疲れた!」という日は休む。このバランスが実はめちゃくちゃ大事だったりする。
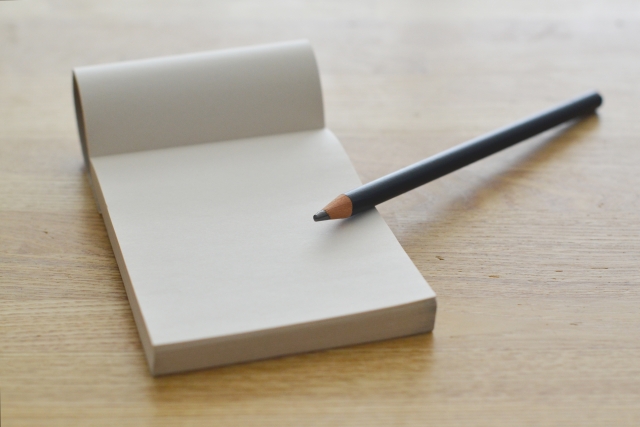
コツ④配色にこだわり過ぎない
「赤ちゃん用に読む絵本だったら・・・とにかく色がハッキリしていて、コントラストもガッツリついていて、赤や黄色やその他のビビットカラーがしっかり入っていて・・・」
ファーストブックにこだわる方は多い。
ハッキリしている方が・・・は一理あるものの、この固定観念に縛られ過ぎる必要もない。なぜなら、新生児期なんてまだまだ視力も発展途上。どちらにしろ、視覚的にはあまりよく認識できていないと考えている方が良かったりする。
産後はパパママが楽しく絵本を読むことを習慣化する期間、と捉えるのが精神衛生的にも一番良い。
世の「赤ちゃん絵本はコレでしょ!」に操られ過ぎず、まずはパパママにとって興味がある絵本、癒される絵本、読んでいて楽しくなる絵本、こういった作品を選んでみるのが吉。
コツ⑤習慣化のゴールを捉える
絵本の習慣化のゴールはズバリ
子どもが自ら「これ読んで!」と絵本を手に取って持ってくるようになること
ちなみに筆者の子のファーストブックは下記の2冊。
Amazon.co.jpアソシエイト
良かったら参考にされたい。